History
会社沿革
- 日清オイリオHOME
- 企業情報サイト
- 会社沿革
100年をつくってきたチカラ。100年をつくっていくチカラ。
戦後復興期 1925年〜1959年 昭和前期
昭和初期、技術の普及により、ガス・電気・水道が家屋にひかれ、生活の近代化が進んだ。それにともない食文化にも洋食化の波がおとずれ、一般の家庭でもサラダ油が使われるようになった。
当社は、ドレッシングやマヨネーズの作り方の実演販売を通して、家庭でのサラダ油の使い方の普及に努め、昭和30年代後半に「日清サラダ油」が家庭用サラダ油のトップブランドに。

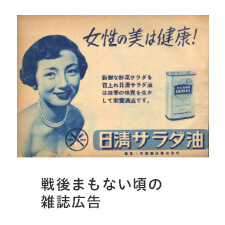
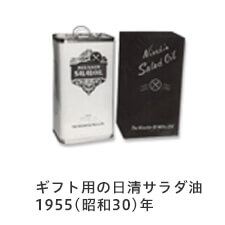

| 昭和初期 |
従来の大豆単一作業から完全に脱皮し、多角的な製油工業としての体制を着々と固めつつあった。精製加工された大豆油は、技術設備の向上とともに次第にその真価が認められてきた。 大不況の時代にもかかわらず、「日清サラダ油」「日清フライ油」のブランド名は着実に一般消費者の間に定着していった。以降、1939(昭和14)年にいたるまで順調に発展したが、日中戦争のぼっ発から、我が国は、戦時体制に移行し、以後は経済統制による原料入手難から生産は減退の一途をたどるにいたった。 |
|---|---|
| 1945(昭和20)年 | 戦災により、横浜工場(旧横浜神奈川工場)を焼失し、また終戦により大連工場その他の在外資産のすべてを失った。残された那須疎開工場、山梨醸造工場を足場に会社の再建に取りかかった。 |
| 1947(昭和22)年 | 長野県に「東濱油脂化学工業株式会社」を設立 |
| 1948(昭和23)年 |
横浜工場の再建に着手、同年12月に完成、翌年1月操業を開始した。 岡山市に「日本糠油工業株式会社」を設立 |
| 1949(昭和24)年 |
食用油(サラダ油、天ぷら油)の生産を再開 「北海製油株式会社」を合併し、小樽工場とした。 東濱油脂化学工業株式会社の社名を「東浜油脂株式会社」に改めた。 |
| 1951(昭和26)年 |
横浜工場に抽出工場を再建し、大豆原料処理が本格化したほか、処理能力においては、ほぼ戦前の状態に復した。 ごま油の生産を再開 日本糠油工業株式会社の社名を「日本興油工業株式会社」に改めた。 |
| 1952(昭和27)年 | 原料事情の好転と横浜工場の充実にともない、那須工場を閉鎖 |
| 1953(昭和28)年 |
同様に小樽工場を閉鎖 関西地方の需要に対応するため、神戸工場を設置、操業を開始 丸紅株式会社が日本興油工業株式会社に資本参加 |
| 1955(昭和30)年 | 横浜工場敷地が全面接収解除された |
| 1957(昭和32)年 | 日本興油工業株式会社の水島工場竣工 |
| 1958(昭和33)年 | 顆粒状レシチンの国産化に成功 |
| 1959(昭和34)年 |
日清製油株式会社が攝津製油株式会社(創立1889年=明治22年、現 セッツ株式会社)の経営に参加 研究部を独立させ、日清製油研究所を開設 |
